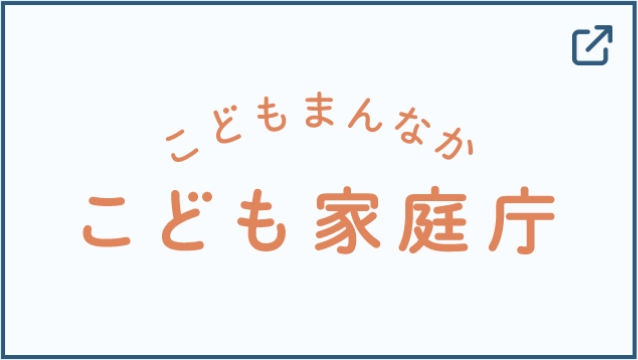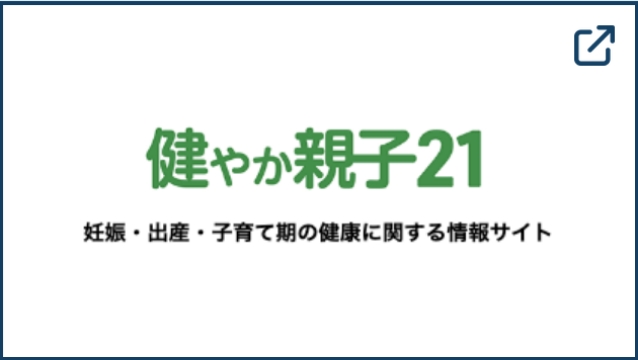食品によるこどもの窒息事故
防ぐための工夫とは?

季節の行事にちなんだ食品や、旬のものを食べることは、こどもにとって大切な食育の一環です。しかし、こどもの嚙む力や飲み込む力が弱く、食品によっては窒息事故につながることもあります。こどもに大切な食育の機会を提供し、こどもが安心して食生活を送れるように、大人ができるひと工夫をお伝えします。
こどもの窒息事故の約9割が5歳未満
食品によるものも含め、こどもの窒息事故は、令和4年までの5年間に407件起きています。その約9割が5歳未満の乳幼児です。

理由はさまざまですが、乳幼児の嚙む力、飲み込む力が弱いこと、こどもは嚙まずに丸のみしがちなこと、大人と違い自分で食べられるかどうかを判断できず、与えられたものを疑うことなく食べることなどが挙げられます。
節分の豆まきに注意
邪気を払い、福を呼び込む節分の豆まきは、2月の楽しいイベントです。
節分の豆を「年の数だけ食べる」という伝統は、親子で楽しみたくなるものですね。
しかし、節分の豆も窒息に注意するべき食品です。節分の豆は食べさせず、豆まきもひと工夫することで窒息を防ぐことができます。節分はほかの方法でも、十分楽しめます。
○個包装の豆をまいたり、折り紙や新聞紙でこどもと作った拳サイズの「紙の豆」をまいたり……節分を安全に楽しむ工夫をしてみましょう。
○個包装の豆をまいた後は、こどもが開けて食べないよう後片付けも忘れないようにしましょう。
○また、節分の豆に限らず、枝豆などの豆類、ピーナッツやアーモンドなどのナッツ類はこどもが丸飲みしてのどに詰まらせやすい食品です。5歳以下の子どもには、食べさせないようにしましょう。
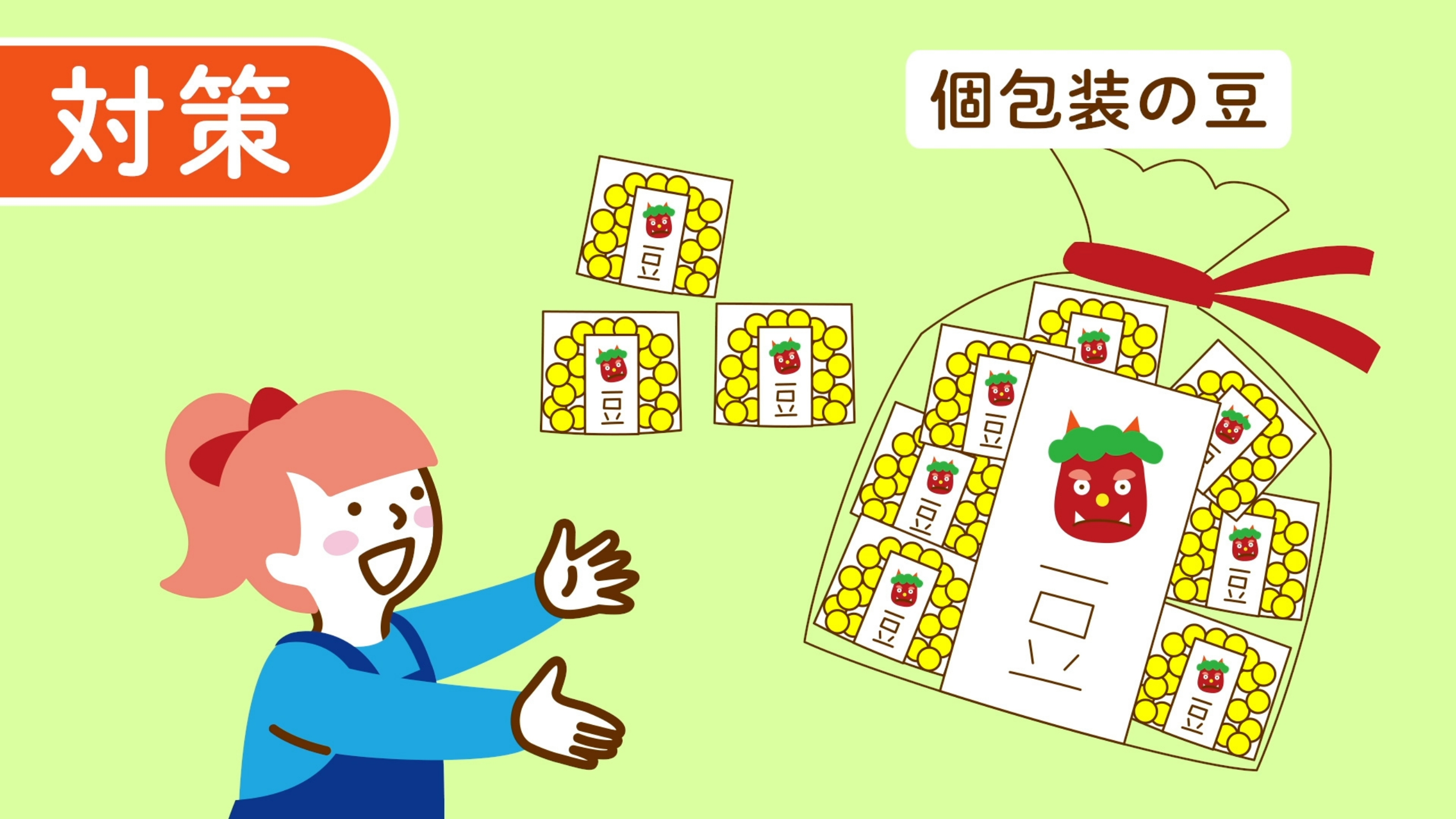
ブドウやミニトマト、食パンなどは
「小さくカット」で対策を
ブドウやミニトマトが好きなこどもは多いです。最近は皮ごと食べられるブドウが主流で、おやつの定番になっています。
実はこれらの「丸くてつるっとした食べ物」も、窒息事故の原因になります。
また食パンなどの、水分が少なくパサパサした食感のものも、うまく飲み込めずにのどに詰まりやすい食べ物です。
こうした食べ物は、カットすることで窒息事故のリスクを減らせます。
○嚙みやすく、飲み込みやすくするため、ブドウ、ミニトマトは4等分、食パンは1センチ角にカットするようにしましょう。
「ながら食べ」はやめよう
こどもはおなかが少し満たされると、食事に集中することが難しくなり、おもちゃで遊びながら食べたり、動画を見ながら食べたりしたがります。
遊びながら食べること、歌ったり話したりしながら食べることは、食べ物をのどに詰まらせる原因になります。
○食事のときはこどもを椅子に座らせて、こどもが食事に集中できる環境をつくり、大人と一緒に食事をとるようにしましょう。
○また、「ながら食べ」とは少し違いますが、食べているときにこどもがびっくりするようなことがあると、驚いて食べ物がのどに詰まってしまうことがあります。こどもを驚かせないよう、落ち着いた環境で食事するようにしましょう。
安全で安心な食事環境で、こどもがこころもからだもすくすく成長できるよう、しっかり事故予防対策をしていきましょう。
知っておきたい、
命の守り⽅の具体策
-

 一般のみなさまへこどもが安全・安心に暮らせる環境をつくるために、普段の生活の中で取り組める予防策を動画や記事でご紹介します。
一般のみなさまへこどもが安全・安心に暮らせる環境をつくるために、普段の生活の中で取り組める予防策を動画や記事でご紹介します。 -

 自治体の方へ各自治体で行われているCDRモデル事業の取り組みについてご紹介します。
自治体の方へ各自治体で行われているCDRモデル事業の取り組みについてご紹介します。 -

 医療機関の方へCDRの実施にあたり、医療関係者のみなさまにお願いしたいことや対応方法についてご紹介します。
医療機関の方へCDRの実施にあたり、医療関係者のみなさまにお願いしたいことや対応方法についてご紹介します。
防ぐための予防策